天候:晴
今回も安近短シリーズとして計画。第3弾である。丹波川はおいらん渕付近で本流の一之瀬川と柳沢川に分かれるが、今回は、柳沢川の支流のタキ沢(滝沢)を遡行し、西隣のタナ沢を下降する計画とした。
タキ沢もタナ沢も、地形図には名称も水線も描かれていない。名称は、昭文社の登山地図に拠った。タキ沢については、ネットや古いガイドブックでは、2段40mの大滝があり、冬季の氷瀑登攀の記録がいくつか見つかったが、タナ沢は情報なし。見どころはタキ沢の大滝くらいだろうとは思ったが、記録のない沢も気になるので、夏季休暇の1日を、探索に充ててみた。

タキ沢へのアプローチは、水源巡視路として現役の旧黒川通りを利用。タキ沢にぶつかるところは崩落していたが、作業用に設置されたらしい比較的新しいロープがあったので、それを借りて急斜面を沢床へ降りた。対岸には、旧道跡が続いており、木橋の残骸も残っていた。タキ沢自体は、しばらくは平凡な渓相だ。5分ほど遡るとモノレールが横切っている。沢のところがスイッチバックになっていて珍しいので、お~とか言いながら写真を撮っていると、人の気配が…。調査のために発破作業をしており、あと1時間ちょっとで作業を始めるとのこと。こちらは、上まで登って隣の沢を降りる予定なので、戻ってはこないと伝えた。写真を撮ったり、遡行図用のメモを取ったりしていたので、何か調査ですか?と聞かれたが、いえ単なる趣味の沢登りで….って答えたのだが、こんなところに来るのは相当なもの好きだと思っただろうなあ…。

さて、閑話休題。
その先は、2~5m程度の滝がいくつか懸かるが、難しいところはない。

モノレールから30分弱で前方の木の間越しに大滝らしき姿が見えてきた。近づいて見ると、水量もそこそこあり、なかなかの見ごたえだ。高さは30mくらいに見える。

下部は、少し傾斜の緩いナメ滝になっている。左の水流沿いは、バンドが3段くらいあるので、少し上の様子を覗いてみた。
半分くらいのところから観察すると、上部5~6mはホールドも少なく登るのはかなり難しそう。上部から巻くのも泥交じりの壁を灌木を頼りに登らねばならず、確保なしではちょっと躊躇う。

その一段下からの方が安全に巻けそうなので、滝の下部1/3ほどのところから、右岸斜面を木の根を頼りに巻いたが、ハチの襲撃を交わしながらになり、少し上まで登りすぎたようだ。最終的には、岩場の間の斜面を懸垂下降して、落ち口のすぐ上に降り立った。もう少し下の滝寄りだと懸垂下降せずに降りられそうだが、逆に、スリップしたら下まで落っこちそうなので、今回は結果オーライだったような気もする。急斜面の登攀で、汗をだいぶかいたので、降り立ったところで、ちょっと一休み。パンをかじって、水分を補給した。そこからも滝がいくつか懸るが、傾斜も緩く快適に越えて行ける。

水流が少なくなると、周囲は起伏の少ない広葉樹の林となり、公園のような風情に。ムジナ沢トノ沢の上部と同じような風景だ。そこに、ポツンとタバコの箱が転がっているのを見つけた。そんなに古くはなさそう。山仕事の人のものか。
Co1350の二俣は、右の方が水量が多い。地形的には本流は左のようだが。隣のタナ沢へ乗っ越すにも、右からの方が都合がいいので、右へ進む。谷が開けていて沢型が判然としないが、しばらく進むと、右手上部に鞍部らしき明かりが見えた。目指す鞍部と思われる、その明かりを目指して斜面を登るが、踏み跡が断続的に現れる。それなりに人は入っているのだろう。しかし、思ったよりも急傾斜だ。最後は大滝の巻きと同じくらい汗をかいて、1528m地点南の鞍部に到着。風が抜けて心地よい。

一息ついて、反対側の斜面を下る。しばらくは、水なしのガレ沢である。先週のホウロク沢と同じだったら…と危惧を感じたが、左岸からの窪をいくつか合わせると水流が出てきてホッとする。

ちょっとナメっぽい流れを下っていくと、前方の谷が狭まり、その先がすぱっと切れ落ちている雰囲気。両岸は短いゴルジュになっている。ゴルジュの奥、狭い岩の隙間から流れが下方へ吸い込まれている。左岸にやや傾斜の緩めな斜面があるが、手掛かりが少なそうだ。面倒なので、丈夫そうな木の根を支点に懸垂下降した。30mロープ1本で、下までは2~3m届かない。もっとも、めいっぱい降りたところからは、傾斜も緩み歩いて下れるので、無事に滝の下へ。ただ、斜面は泥でぐずぐずだ。下から見ると、右岸斜面は傾斜が緩いので、そちらからなら歩いて下れそうだが、ゴルジュ手前から岩場を大回りをする必要がありそう。滝の高さは15m滝というところか。タナ沢という名称から、多少は滝場があるのでは、と想像していたが、思ったより大きな滝があり、なんだか儲けた気分。もっとも、水量が少なくタキ沢の大滝ほどの迫力はない。タキ沢大滝を「動」とすると、「静」の滝という感じで好対照だ。

大滝から下流は、ところどころに小さな滝を懸けてやや変化が出てくる。30m程のナメや樋ナメ状になった箇所もも見られ、そこそこ楽しく下って行く。

タナ沢は、棚のような段々の小滝が多いことからの名称かしら?などと想像をする。いやいや、実は出合に棚状の滝があったりしてと少し期待するが、傾斜が緩んでくると、前方に柳沢川の流れが見えるようになり、本流との出合は平凡なゴーロで、しかも伏流気味…ちっとも映えないのであった。




対岸は、放棄された農地と思しき空き地と、隣接して空き家らしき建物が建っている。本流を徒渉してから、空き地を横切ると、すんなりと国道に出られる。駐車地点まではほんの数分の距離で、楽ちん。

今日は、大きな滝も見て、懸垂下降だが安近短シリーズでは初めてロープを使う沢登りとなり、小さな沢ながら思ったよりも充実した内容になった。
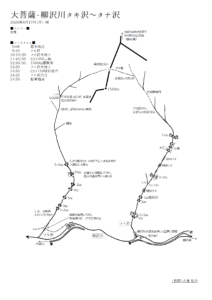
駐車地点(9:08)-タキ沢(9:40)-大滝下(10:10/20)-Co1350二俣(11:45/55)-1500m圏鞍部(12:30/35)-タナ沢大滝下(13:25)-Co1150枝沢出合(13:55)-タナ沢出合(14:25)-駐車地点(14:33)